

(さかもと はんじろう)は、明治・大正・昭和にわたり活動した近代洋画家であり、印象派の技法を基盤としながらも、東洋的な精神性と内面性を融合させた独自の画風を確立しました。
柔らかな光、穏やかな空気、そして画面に宿る沈黙——それらを通して、坂本は見る者の心に静かに語りかける絵を描き続けました。
その筆は、騒がしさや派手さを退け、自然との深い対話から生まれた“精神の風景”として、日本近代洋画のなかに深い静けさを刻み残しています。
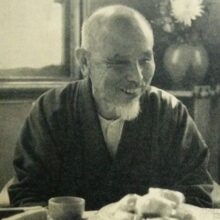
1882年、福岡県久留米市に旧有馬藩士の家に生まれる。幼少から絵に親しみ、1892年には地元の洋画家・森三美に師事。1902年には親友・青木繁とともに上京し、小山正太郎の不同舎に入門。
1904年には太平洋画会研究所に移り、以後、太平洋画会展や文展に出品を続け、1907年には東京府勧業博覧会で《大島の一部》が三等賞を受賞。第1回文展にも出品するなど、画壇での存在感を高めていった。
1914年には在野の二科会創立に参加。1921年から3年間はパリに留学し、西洋の美術潮流に直接触れながらも、東洋的精神に根ざした画風を探求した。
1931年以降は福岡県八女市に居を構え、馬、能面、月などを静かに描き続けた。1954年には毎日美術賞、1956年には文化勲章を受章し、1969年、87歳で永眠。
坂本の作品は、印象派の柔らかい光と色彩感覚を取り入れつつも、絵画に“見ることの深さ”を宿そうとする東洋的な静謐さが特徴です。
初期には牛や牧場の風景を通じて生活と自然の一体感を描き、晩年には能面や月を題材に、内面世界の象徴性を深めました。
とくに《水より上る馬》《能面》などは、単なる写実にとどまらず、余白や静けさによって“見えないもの”を感じさせる力を持ち、東西の美学を融合させた表現として高く評価されています。
坂本の絵には、描かれたもの以上に“描かれていない空気”があり、それが観る者の心に、深く染み入る余白を残すのです。
●《大島の一部》(1907年)
文展出品作。島影の静かな佇まいと淡い色調が、後の坂本芸術の萌芽を示している。
●《うすれ日》(1912年)
日常の光景のなかに、微細な光と空気の揺らぎをとらえた名作。夏目漱石も絶賛した作品。
●《放牧三馬》(1932年)
馬というモチーフを通じて自然と生命の一体感を描写。画面に漂う詩情が美しい。
●《水より上る馬》(1953年)
水面から現れる馬体が、象徴的かつ静謐に浮かび上がる。代表的な晩年の油彩。
●《能面》(1955年)
静かにたたずむ能面の表情を描くことで、人間の内面を象徴的に表したシリーズ。
坂本繁二郎の作品は、文化勲章作家として高く評価されており、特に馬や能面、月を題材とした油彩画は安定した高額評価を得ています。
⚫︎油彩作品(30号前後) 500万円〜2,000万円超
⚫︎戦前の牛・馬モチーフ作品は1,000万円〜4,000万円級の評価もあり
⚫︎素描・水彩・スケッチ類も状態やサイズにより数十万円〜数百万円で取引
近年は再評価が進み、美術館収蔵作品と並ぶ品質の真筆作には、国内外のコレクターからの注目も高まっています。
以下の条件を満たす作品が特に高く評価されています。
⚫︎1930年代以降の馬や月の作品(東洋的象徴性が明確なもの)
⚫︎能面シリーズの代表作
⚫︎漱石や二科展関連の来歴ある作品
⚫︎パリ留学期の写生やスケッチブック(資料価値高)
また、小品であっても、坂本らしい静謐な空気感をまとった作品は安定して人気があります。真贋・来歴の明確さが市場評価に直結する作家です。
坂本繁二郎の作品には、大きな声では語られない深さがあります。
光を描くのではなく、“光の気配”を描き、対象のかたちではなく“余韻”を画面にとどめる。
その静かな表現は、現代の美術においても色褪せることなく、観る者に問いかけを残し続けます。
ご自宅やご実家に坂本繁二郎作品をご所蔵の方は、専門家による鑑定・査定をぜひご検討ください。
馬・能面・月シリーズなど専門対応/写真で簡単査定受付中







