

光と筆致で風景に東洋の詩情を宿した近代洋画の重鎮
金山平三(かなやま へいぞう)は、明治・大正・昭和を通して日本洋画の発展を担い続けた重鎮であり、近代官展制度の中心で活躍した実力派洋画家です。
西洋画法を学びつつ、確かな観察眼と練達の筆技によって、風景や静物に日本的抒情を宿したその作品群は、自然と対峙する深いまなざしと画面構成の静謐さにおいて特筆すべきものがあります。
1900年代初頭に東京美術学校を卒業した後、1912年にはヨーロッパに渡り、各地を遊学。帰国後は文展・帝展で次々と特選を受賞し、帝展審査員も長らく務めました。戦後は官展から距離を置き、個展中心の活動へと移行。芸術院会員、帝室技芸員としてその画業は国に認められ、昭和洋画の礎を築いた一人として現在も高く評価されています。
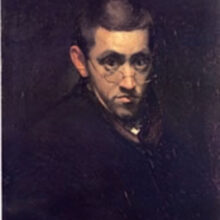
1883年(明治16年)、兵庫県神戸市に生まれる。
1909年(明治42年)、東京美術学校西洋画科本科卒業。卒業後、同校助手を務める。
1912年(明治45年)、渡欧。フランスを中心にヨーロッパ各地を巡歴し、1915年(大正4年)帰国。
1916年〜1925年、文展・帝展にて《夏の内海》《氷すべり》などで特選を受賞。以後帝展審査員を歴任。
1935年(昭和10年)、帝国美術院改組に際し、官展から離れ独立した発表活動へ。
1944年(昭和19年)、帝室技芸員に任命。
1957年(昭和32年)、日本芸術院会員となる。
1964年(昭和39年)、逝去。享年80。
金山の作品は、外光派の伝統に基づきながらも、日本的な静けさと構造感覚を画面に融合させており、洋画における“詩的写実”の一つの到達点といえるものです。
⚫︎外光派の素地と確かな写実(1910年代〜1920年代)
初期はヨーロッパでの写生や観察に基づいた風景表現が中心。写実的ながらも温かみのある光や筆致が特徴で、文展での特選作にその端緒が見られる。
⚫︎東洋的抒情と西洋構成の交錯(1920〜30年代)
帝展において高く評価された一連の作品群では、構図の安定感と淡い色調により、静けさを湛えた日本的情感が際立つ。特に《菊》《下諏訪リンク》などに代表される。
⚫︎官展離脱と個展への移行(1935年以降)
帝国美術院改組に際して官展から距離を取り、独自のスタイルを深化させる。個展を中心とした発表では、素材や筆致の研究も進み、より軽やかで洗練された画面を志向。
⚫︎晩年の静物・植物画と精神性(戦後〜1950年代)
菊、ダリアなどの花を中心とした静物作品に重心を移し、構成美と質感描写が高度に統合された画面へ。写実にとどまらない、精神性の表現としての油彩表現が確立される。
⚫︎1910年代(渡欧期〜帰国直後)
代表的展開:ヨーロッパ風景や都市描写をテーマに、外光派的手法を吸収。
市場での見どころ:留学期の作品や帰国後直後の文展入選作など、画歴上の転機にあたる作品群が注目される。
⚫︎1920年代(文展・帝展での活躍期)
代表的展開:《夏の内海》《氷すべり》《菊》などを中心に、自然と人間の調和を描く詩的風景画。
市場での見どころ:帝展出品作の中でも特選や買上作品は安定した評価を受けており、状態・出展履歴によって高く評価される傾向。
⚫︎1930年代〜1940年代(構図と抒情の深化)
代表的展開:《下諏訪のリンク》《信濃路》など、雪景や花を通じて構造と感情を両立させる画風に展開。
市場での見どころ:宮内省買上作品や帝室技芸員任命後の制作など、歴史的意義のある作品群に特に関心が集まる。
⚫︎1950年代(晩年・静物中心の時期)
代表的展開:花や器物を中心とした静物作品に構図の洗練と筆致の深みが見られる。
市場での見どころ:技術と構成の集大成として、晩年の静物画は再評価の対象。保存状態やシリーズ構成による希少性も加味される。
金山平三の作品は、日本の風景や静物に静かな詩情を宿し、油彩でありながら東洋的な美意識をたたえた独自の表現で、多くの人々の記憶に残る画業を築いてきました。
官展制度の中で磨かれた確かな技術と、自然や対象物への深いまなざしは、戦前・戦後を通じて一貫した魅力として現在にも響いています。
近年では、文展・帝展に出品された代表作や、帝室技芸員任命後の円熟期の作品、そして晩年の静物画に対する評価が国内外で高まりつつあり、美術市場でも安定した人気を保っています。とくに、展覧会歴や由来が明確な作品は収集家・専門機関からの関心も高く、ご所蔵の金山作品を手放すには非常に好機といえるタイミングが訪れています。
大切な作品が、次の世代へと受け継がれていくために。
一点ごとの価値を丁寧に見極め、最適な方法で未来へつなげていくお手伝いができれば幸いです。
官展洋画の確かな価値を未来へ/金山平三のご売却・ご相談承ります。







