

理知と抒情で写実を再構築した、日本近代洋画の巨峰
安井曾太郎(やすいそうたろう)は、昭和期の日本洋画界において、梅原龍三郎と並び称された重鎮画家です。
フランス留学時代にセザンヌに深く傾倒しつつ、日本的な美意識を融合した独自の「安井様式」を確立。その洗練された理知的写実は、婦人像や風景画において圧倒的な存在感を放ちました。
教育者としても多くの後進を育て、日本洋画の成熟を導いた安井の筆は、感性と構成、直観と理論を見事に調和させた「近代美術の知性」そのものでした。
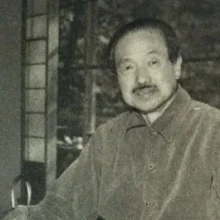
1888年、京都市の木綿商家の五男として誕生。商業学校を中退後、聖護院洋画研究所(関西美術院)に学び、浅井忠・鹿子木孟郎に師事。梅原龍三郎とは同期であった。
1907年、フランス・パリに留学し、アカデミー・ジュリアンでジャン・ポール・ローランスに師事。セザンヌの作品に衝撃を受け、理知的な構成感覚と造形意識を養う。
第一次世界大戦の勃発と健康上の理由で1914年に帰国。翌1915年の第2回二科展にて滞欧作44点を一挙出品し、大きな注目を集め二科会会員となる。
1930年代には「安井様式」とも称される日本的写実のスタイルを確立。1935年には帝国美術院会員となり、翌年に二科会を退会。一水会の創立に参加し終生委員として活動。
1944年、東京美術学校教授に就任し、戦後も教育者として活躍。1952年に文化勲章を受章し、1955年に逝去。享年67。
安井曾太郎の画風は、「写実を超えた写実」とも言われる理知的構成美に満ちています。
セザンヌに学んだ構築的な描写を基盤としながらも、日本的抒情性と色彩感覚を加えた彼の絵画は、堅固でありながらも静かな品格をたたえています。
とりわけ婦人像では、モチーフに対する適度な距離感と、洗練された色彩の調和が見られ、どこか静謐な精神性を感じさせます。
1930年代以降には、風景画や静物画にも独自の造形美が現れ、まさに「安井様式」と称される完成度を獲得しました。
●《金蓉》(1934年)
黒い衣装の婦人像を描いた名作。余白と輪郭の緊張が生む静けさが、安井様式を象徴する。
●《婦人像》各種
大正から昭和にかけて多く描かれた安井の主題。造形と色彩の安定感が際立つ。
●《静物(果物)》
構成美と色彩のバランスが光る静物画。セザンヌ的感覚と日本的余白美の融合がみられる。
●《風景(比叡山)》
抑制された筆致の中に、自然への敬意と構成への執着が共存する秀作。
安井曾太郎の作品は、日本近代洋画の金字塔として美術館収蔵が進んでおり、特に婦人像や昭和期の静物・風景画においては市場でも非常に高い評価を受けています。
⚫︎婦人像・代表的油彩:1,000万〜6,000万円以上
⚫︎小型風景画・静物画:300万〜1,200万円前後
⚫︎素描・デッサン:100万〜500万円(来歴や保存状態による)
文化勲章受章者としての格式と、学術的にも評価の高い安井作品は、今後も安定した価値が期待されています。
特に評価が高いのは以下のような作品群です。
⚫︎昭和初期〜中期の婦人像、黒衣の人物像
⚫︎サロン・ドートンヌ出品歴、帝展・文展の受賞作・関連作品
⚫︎一水会出品作や、美術館展覧会に掲載された作品
⚫︎画集・文献に掲載歴のある代表的構図の油彩画
サインや裏書の有無、東京美術学校教授時代の記録など、来歴の明確さが査定額に直結します。
安井曾太郎の筆は、単なる模写ではなく、対象の本質を「構成」し直すという写実の新たな地平を切り開きました。
絵画に求められる厳格さと、美しさへの静かな情熱。その両立を成し得たからこそ、彼は“安井様式”として後世に名を残したのです。
ご自宅やご実家に安井曾太郎の作品をご所蔵の方は、ぜひ専門家による査定をご検討ください。
婦人像・静物・風景まで幅広く対応/文化勲章作家専門査定受付中







