

三島喜美代(みしま きみよ)は1932年大阪市生まれ、2024年に逝去した日本を代表する陶芸家です。1950年代から絵画制作を始め、1960年代以降は新聞や雑誌の印刷物を陶に転写する独自技法で知られるようになりました。この「割れる印刷物」シリーズでは、情報が物理的に割れる陶器に封じ込められ、消えゆく情報の儚さを象徴的に表現。空き缶や段ボールといった廃棄物を陶でリアルに再現することで、現代社会の環境問題や物質文化への問いかけも盛り込みました。1980年代以降は大型インスタレーション《20世紀の記憶》など、情報の集積や消失をテーマにした作品も発表し、国内外で高く評価されています。
た廃棄物を陶でリアルに再現することで、現代社会の環境問題や物質文化への問いかけも盛り込みました。1980年代以降は大型インスタレーション《20世紀の記憶》など、情報の集積や消失をテーマにした作品も発表し、国内外で高く評価されています。
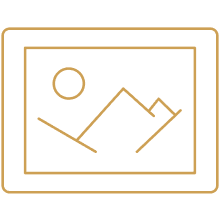
《割れる印刷物》シリーズ:新聞や雑誌の情報を陶に転写し、物理的な「割れ」を通じて情報の消失を表現。
《20世紀の記憶》:約1万個の陶レンガに新聞記事を転写し床一面に敷き詰めた大型インスタレーション。
空き缶・段ボールの陶彫刻:現代の廃棄物を精緻に陶で再現し、社会批評を含む作品群。
《もうひとつの再生》(直島ベネッセハウスミュージアム所蔵):高さ5メートルの巨大ゴミ箱インスタレーション。
三島は2022年に毎日芸術賞を受賞、2021年の森美術館「アナザーエナジー展」への出展で注目を浴びました。2023年には岐阜県現代陶芸美術館、2024年には練馬区立美術館で大規模回顧展を開催。東京都現代美術館や京都国立近代美術館をはじめ、国内外の主要美術館に作品が収蔵されています。
三島喜美代は、陶を媒介にして消えゆく情報や廃棄物を「化石」として封じ込める独創的な技法で、現代社会への批評とユーモアを融合させた陶芸の先駆者です。彼女の作品は日本だけでなく国際的にも高く評価され、現代陶芸の重要な位置を占めています。所有する作品の査定や売却を検討される方は、専門家による正確な評価を受けることをおすすめします。
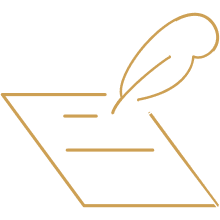
三島の作品は国内外の美術市場で安定した人気を誇り、特に《割れる印刷物》シリーズの陶板作品やインスタレーションの一部は高額で取引されています。作品の規模や保存状態、展覧会出品歴などが査定価格に大きく影響するため、正確な評価には専門的な査定が推奨されます。







