

伊藤久三郎(いとう・きゅうざぶろう)は、京都に拠点を置きながら、日本の抽象絵画黎明期における先駆者として、戦後前衛美術の地平を切り拓いた洋画家である。
「ハムのある静物」で二科展に初入選して以降、静物画から出発した彼の絵画は、やがて抽象と幻想を交錯させる空間へと深化し、「遮蔽」「地表」「猜疑」など、見る者の深層を揺さぶる重層的な作品群を遺した。
行動美術協会の創立メンバーとして、また京都抽象絵画の草分けとして、地に根ざした静かな闘志と理知を絵具に託し続けたその軌跡は、関西美術史における重要な一頁をなしている。
1906年(明治39年) 京都市下京区に生まれる
1918年(大正7年) 京都市立美術工芸学校に入学
1923年(大正12年) 同校絵画科本科を卒業
1924年(大正13年) 京都市立絵画専門学校本科(日本画)に入学
1928年(昭和3年) 同校卒業、東京・駒込に移住し、1930年協会洋画研究所に通う
1931年(昭和6年) 第16回二科展に「ハムのある静物」で初入選
1933年(昭和8年) 佐野繁次郎らと新油絵展を結成
1936年(昭和11年) 新美術家協会に入会
1938年(昭和13年) 九室会に参加(二科会前衛グループ)
1941年(昭和16年) 二科会会員となる
1945年(昭和20年) 京都に帰郷、行動美術協会の創立会員に迎えられる
1953年(昭和28年) 「抽象と幻想」展(東京国立近代美術館)に《イカルス》を出品
1956年〜57年 日本国際美術展、現代日本美術展、サンパウロ・ビエンナーレなどに相次ぎ出品
1971年(昭和46年) 京都市美術館評議員に就任
1976年(昭和51年) 京都府美術工芸功労者に選出
1977年(昭和52年) 逝去(享年71)
教育者としても、日吉丘高校や成安女子短大などで若い才能を育成した。
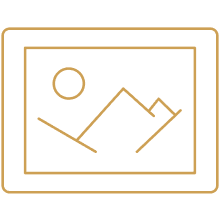
具象から抽象へ──「遮蔽」と「地表」にみる視覚の深層
伊藤の作品は、その初期において静物を主題とする具象画から始まったが、戦後まもなく大きく転回を見せる。
1940年代後半以降、彼の関心は「構造」と「幻想」、あるいは「記憶」と「無意識」といったテーマに移り、やがて《遮蔽》《猜疑》《地表》といったタイトルに象徴される、地層のように積み重なる絵画空間が展開された。
とりわけ《地表》は、地質学的断面のような視覚構成の中に、内面の沈潜を重ね合わせたものであり、戦後日本の抽象絵画における精神性の深さを象徴する重要作として知られる。
国内外で評価された戦後前衛の表現者
1950年代から60年代にかけて、東京国立近代美術館、サンパウロ・ビエンナーレ、日本国際美術展、現代日本美術展などで継続的に発表を行い、国際的にもその存在感を高めた。
また、1971年に京都国立近代美術館で開催された「前衛絵画の先駆者たち」展では、《流れの部分》《合歓の木》《振子》などが出品され、関西における抽象絵画運動の系譜における重要作家として位置づけられた。
彼の作品は、行動美術展を中心に出品され続け、以下のような代表作が知られている:
《遮蔽》(第8回行動展)
《猜疑》(第9回)
《ラプソディー66》(第21回)
《作品70A》(第25回)
《773-B(劃)》(第28回)
《75a(地)》(第30回)
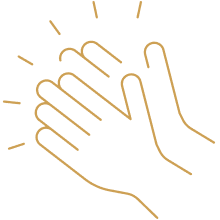
伊藤久三郎は、絵画を通して「現実を遮蔽するヴェール」を可視化しようとした。
それは、対象を再現するのではなく、対象の内にある不在、沈黙、記憶といった不可視のものを画面上に引き寄せる試みであった。
京都に根ざしながらも、日本の戦後前衛美術と抽象絵画の歩みに確かな刻印を残した彼の画業は、今なお過小評価されていると言ってよい。
しかしながら近年、行動美術や戦後関西画壇の再検証が進む中で、伊藤の作品も再び光を浴びつつある。
“地表”を描いた画家は、同時に“記憶の深層”を描いていた──。
その絵画的営為は、いま再び、私たちの視覚と内面に問いを投げかけている。
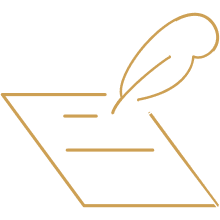
査定時に重視される要素
⚫︎作品に署名・落款(朱印など)があるか
⚫︎保存状態(絹本や紙本の劣化・折れ)
⚫︎額装の有無と状態
⚫︎展覧会出品歴やカタログ掲載の有無
⚫︎抽象性が高く、構成が完成された作品かどうか
また、伊藤久三郎の作品は似た名前の作家との混同もあるため、真贋判断は経験のある専門家が行う必要があります。
LINEで写真を送って簡単査定







