

丸山直文(まるやま なおふみ)は、にじみやぼかしを活かした独自の絵画技法で知られる現代アーティストです。水を含ませた綿布にアクリル絵具を染み込ませる「ステイニング」の手法を用い、風景や人物、抽象的な形象を曖昧な輪郭で描き出します。その作品は、見る者に時間や場所の記憶を呼び起こすような、詩的で幻想的な世界を提示します。
1964年、新潟県に生まれた丸山は、文化服装学院やセツ・モードセミナーで学び、Bゼミスクーリングシステムを修了しました。1990年代初頭から活動を開始し、有機的な形態を大画面に描く抽象画で注目を集めました。2008年には目黒区美術館で個展「後ろの正面」を開催し、同年、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞しています。
主な個展には、「水を蹴る」(シュウゴアーツ、東京、2022年)、「ラスコーと天気」(シュウゴアーツ、東京、2018年)、「流」(ウソンギャラリー、韓国、2017年)などがあり、国内外で精力的に作品を発表しています。
丸山の作品は、下地材を施していない綿布に水を含ませ、アクリル絵具を染み込ませることで、色面と線の境界が溶け合う独特の表現を生み出しています。この技法は、偶然性と制御のバランスを取りながら、硬さと柔らかさ、自然と人工、主観と客観といった相反する要素を画面に共存させています。
特に「水」は彼の作品において重要なモチーフであり、東日本大震災の際には、アトリエで描いていた作品の表面に張った水や絵の具が揺れ動く様子が、津波で流された街の映像と重なり、自身の立つ場所の不安定さを実感したと語っています 。
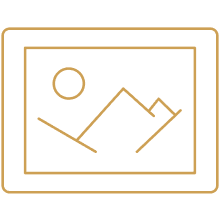
《水を蹴る(そこに)》(2022年)
水面に映る風景が揺らぎ、現実と幻想の境界が曖昧になる作品。ポーラ美術館で開催された「水を蹴る―仙石原―」展で展示されました。
《水を蹴る・仙石原(そこでは)》(2023年)
箱根・仙石原の森を取材して描かれた新作。湿潤な土壌で育つヒメシャラの木々が描かれ、水と森の関係性を探求しています 。
《camp2》
グレーを基調としたモノクロームの作品。色彩を抑えることで、より深い感情や記憶を呼び起こす効果を狙っています。
丸山直文の作品は、国内外の美術館やギャラリーで高く評価されており、近年ではアートフェアやコレクターズイベントでも注目を集めています。特に、シュウゴアーツでの個展やポーラ美術館での展示を通じて、その独自の表現手法と詩的な世界観が再評価されています。
市場価格の目安は以下の通りです。
⚫︎中〜大サイズの作品:50万〜150万円
⚫︎小作品・ドローイング:30万〜80万円
作品のサイズやシリーズ、展示歴などによって価格は変動しますが、今後も評価の高まりとともに市場価値の上昇が期待されます。
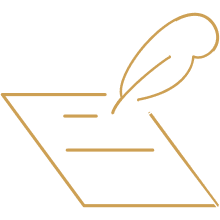
ART Billionでも丸山直文の作品に関する査定依頼が増加しており、以下の条件に該当する作品は特に高評価が期待されます。
⚫︎展覧会出展歴や図録掲載のある作品
⚫︎代表的なシリーズ(例:「水を蹴る」シリーズ)
⚫︎サイン・証明書の付属する作品
⚫︎状態が良好なもの(にじみやぼかしの表現が損なわれていない)
また、作品の背景や購入経緯の説明が査定において重要になる場合があります。
丸山直文の作品は、にじみやぼかしを通じて、見る者の記憶や感情を呼び起こす詩的な力を持っています。水や風景といったモチーフを通じて、現代社会の不安定さや個人の内面を静かに問いかけるその表現は、今後も多くの人々に深い感銘を与え続けるでしょう。
ご自宅に丸山直文の作品をお持ちの方、またはご家族からの相続・整理をご検討中の方は、ぜひ当社の専門査定をご活用ください。







